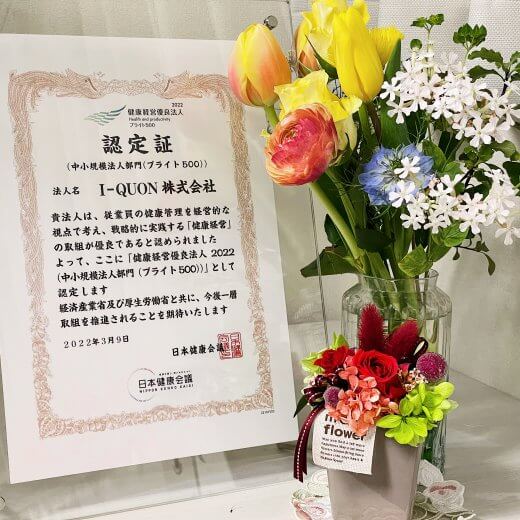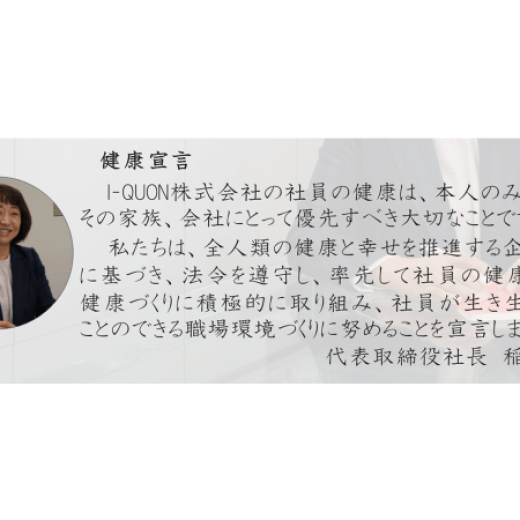キーワード:社交不安傷害、社交不安症、適応障害、発達障害
【事例】
24才 女性。
入社後数年が経過する女性社員。最近コールセンターへの異動が決まったが、電話に出られないという。
本人から話を聞くと、電話は昔から苦手だったとのこと。また、電話だけでなく、学生時代には本読みなども緊張し、人前での発表の日に学校を休むこともあった。入社時の新入社員研修でも、人前で挨拶をしたり上司に言葉を指摘されたことが苦痛だったため上司を避けるようになった。以前の部署では、電話が鳴っても、他の人が出るのを待ったり、席を立ったりするなどして、電話に出なくて済むようにしていた。以前の部署の上司からもヒアリングを行ったところ、本人が電話を取らないことや、仕事でミスがあっても報告しないことに対し、たびたび注意をしていたとのこと。本人は「別の仕事にしてほしい」と訴えている。
本事例のできごとは、もともと社交不安の素因があり、部署異動によって問題が顕在化しています。社交不安障害/社交不安症は、就職や異動・昇進などの役割や職責の変化といった環境変化で生じることが多い病気です。
医学的な観点から
社交不安症は、早い人だと、人の視線が気になる思春期前ごろに発症することが多い精神疾患です。人前で話をするときに過度な緊張があったりうまくいかなかった等の経験によって、一度人前で苦手に感じると、「また不安や恐怖を感じるのではないか」と予測してしまうことで、苦手意識が高まります。また、苦手な場面で、発汗や震え、また過呼吸や動悸などの強い発作が伴うこともあり、徐々に苦手な状況を避けるようになります。なんとか避けられている段階では問題は表面化しませんが、この事例のように、部署異動により電話を取らざるをえなくなったことで社交不安症が発症するといったことも多いと考えられます。また、緊張を少しでも抑えようとして、人と会う前にアルコールを摂取したりする方も多く、アルコール依存症とも関連が深い疾患です。
一方、本人からは、「部署移動でしんどくなった」といった訴えや、不眠や食欲不振などのストレス反応を話されることも多いため、医療機関でも単なる適応障害、抑うつ状態と間違われやすい疾患でもあります。そのような場合であってもよくよく話を聞くと、実は「人との関わりで緊張があった」など、社交不安場面が背後に隠されていたというケースも多くあります。また、社交不安では人前でのパフォーマンスを評価される場面では過度な緊張が出てくるため、初対面の医師や病院での心理検査場面が苦手な場面となり、緊張して話ができず、本来の能力が発揮できないことがあります。しかしながら、対人関係における困難感の部分だけに焦点が当てられてしまい、「人間関係が上手くいかないから発達障害ではないか」等といった安易なレベリングをされてしまうケースもあると言われています。このように、社交不安症は誤診されやすいといった特徴があるため、正しい鑑別が必要です。
労務管理の観点から
周囲から見て、社交不安が疑われる場合でも、本人が困りごとを感じていない場合もあります。そのため、安易に社交不安とラベリングしないよう注意しましょう。一方で、社交不安の有無にかかわらず、業務上でなんらかの問題やストレスが見受けられたり、本人からの訴えがあったりする場合は、話を聞きましょう。
まず、本人が困っているかどうかが問題となりますが、本人から「電話に出るのが怖い」という訴えがあった場合、電話の対応マニュアルを作る、困ったときに相談できる人を作るなど、業務管理の範囲内でできることがあります。
一方、電話がかかってこない職場へ配置転換させたり、上司の報告を避けられるようにするなど、苦手なことを避けられるよう配慮することには慎重である必要があります。場合によっては周囲の人から「本人のわがまま」と捉えられてしまい、人事上の評価も下がってしまうなど、本人の不利益となりかねません。社交不安症状に対して何かしらの就業状の配慮を行う場合は、必ず本人に専門医療機関を受診してもらい、主治医の意見を求めるようにしましょう。
社交不安症は、治療をすれば良くなる病気です。さらに、苦手な状況に意図的に身をおいていくエクスポージャー療法(曝露療法)が有効であるため、治療を受けながらチャレンジしていける環境を整えてあげると、苦手を克服できる可能性があります。その際には、主治医に意見を求めたり、産業医とも相談しながら、少しずつ段階的にチャレンジしていけると効果的でしょう。
一方、どうしても電話業務がしんどい場合は人事労務担当者や産業医等と相談し、休職を勧める必要もあるかもしれません。
病気とまではいかなくても、社交不安傾向がある人は多くいると考えられていますが、まだまだ一般にはよく知られていない疾患です。パニック症などと合わせて、不安障害全般についての基礎知識や緊張のメカニズムについて、研修を行っておくことも役に立つかもしれません。
産業保健ノート:社交不安症
I-QUONでは、事業所でのメンタルヘルスをはじめとした安全衛生管理体制の構築のためのサポートなど、手厚いコンサルティングを心がけております。医療法人を母体とした企業であり、従業員様の健康に関するご相談なども受け付けております。お気軽にお問い合わせください。